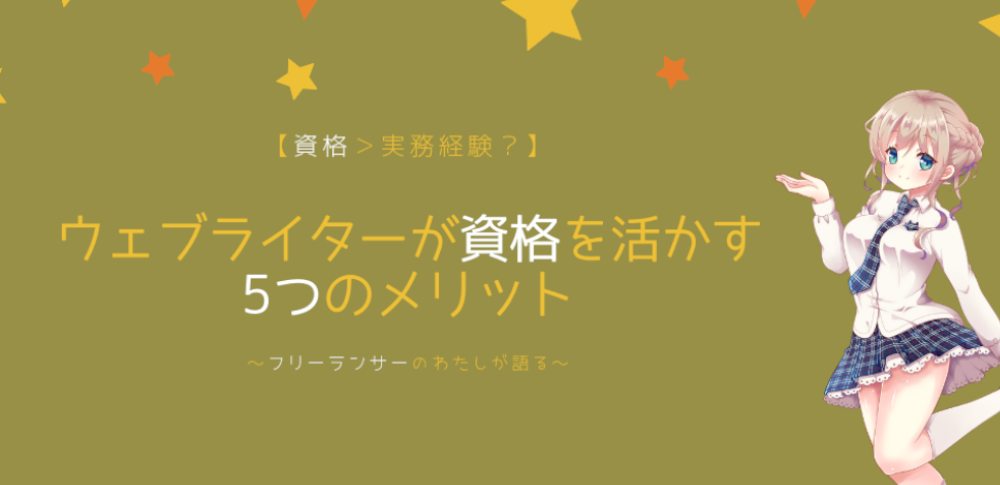
在宅ライターのみなさんは、資格や検定などライセンス的なものを、お持ちでしょうか。
サラリーマン時代に取得した資格を箪笥の肥やしにしている方など、多いのではないかと考えます。
そう。「もう使うコトはないだろう…」と思っているアナタのことです。
その資格、ウェブライターとして活用すれば、思わぬ大金を生み出すかもしれません。なぜなら、ウェブライティングと資格は非常に相性が良いからです。
今回は、ウェブライティングと資格の親和性についてお話しようと思います。

メリット1:人は「専門家」を信用する
まずは実験してみましょう。
新生活を迎えたアナタは地元を離れ、東京都に引っ越しました。ところが、慣れない一人暮らしは大変で、「美味しいごはんの炊き方」に迷っています。
そこでネットで相談したところ、下記2人からアドバイスがもらえました。
アナタは、どちらを信用しますか?
選択肢
- 料理関係の有資格者「炊飯の前に30分ほど水につけると、ふっくらしますよ」
- 職業不詳の人「30分ほど水につけてから炊飯しましょう。美味しくなります」
上記はどちらも、「ご飯を炊く前に水につけよう」と主張している点は変わりません。
しかし、多くの人は職業不詳の人の言葉より、料理関係の有資格者のアドバイスを信用するでしょう。
その理由は、ただひとつ。
アドバイスをしている人が「その分野の専門家」だからです。専門家というフレーズは、「それだけで信じてもらえる」強力な信用力を発揮します。
メリット2:サイトでは「一般のひと」に逆転のチャンスなし
「でも、実際はなしてみたら、一般のひとの方が正しいと感じることもあるのでは?」
当然、出てくるギモンです。意見が対立したときなど、実際に「一般のひとの意見の方が、正しかった」というケースもあるでしょう。
しかし、サイトコンテンツである限り、こうした逆転劇はあり得ません。
なぜなら、サイトコンテンツは「書いてあることがすべて」だから。
サイトコンテンツは基本的に、書いている人が一方的に情報を発信するスタイルです。ツイッターや掲示板のように、プロと一般のひとがその場で議論を交わし、正しい答えを導き出すなどはありません。
一般のひとにチャンスがあるとしたら、「プロのアドバイスが間違ってる」と読者が感じたときだけでしょう。話題が専門領域になればなるほど、人はテーマに対して権威性を求めます。

メリット3:同じようなコンテンツでも「強く」なる
同じようなコンテンツが並んだときも、専門家は強いです。
たとえば、インターネットであるキーワードを検索すると、「似たような情報がたくさん出て来た」という事象がよくあります。
これは「あるサイトを別の人がパクっているから」とか、そういう話ではなく、世の中のほとんどの情報は「だいたいの答えが決まっている」からです。
例えば、「美味しいご飯の炊き方」を説明するなら、
- お米の量を測る
- 水で適度に研ぐ
- 炊飯ボタンを押す
で完了します。
ひと(サイト)によって「炊飯に適した水を使う」、「少しだけお酒を入れる」などの工夫はあるかもしれませんが、基本の流れは変わりません。
だから、わたしたちが「美味しいご飯の炊き方」で検索すると、同じようなコンテンツが並んでしまうというわけです。
さて、ここからが本題。
「美味しいご飯の炊き方」を検索した結果、下記のような表示が出たとします。みなさんはどのサイトが「正しそうだな」と信じますか。
- ごはんの専門家による美味しい炊き方の説明書
- 〇〇米の美味しい炊き方│お米のことなら〇〇食品
- 「お米の美味しい炊き方とは?」経験10年のわたしが教える
- お米の美味しい炊き方教えます
- ライセンス有のプロが伝授!「初心者でもカンタン!美味しいお米の炊き方」
多くの人はまず、一番上のサイトを閲覧します。
しかし、アナタが「このサイトの説明は、どうも難しい」と感じたら?
次に手が出てくるのは、「専門家が優しく教えてくれそうなサイト」ではないでしょうか。あるいは「初心者向けを前に出したサイト」かもしれません。もっとも、その後者の場合も食品会社や専門家など、信頼性の高そうなところが良さそうです。
検索している人のレベルにもよりますが、「専門家」というだけで、選択候補にあがってくる点だけは間違いなさそうです。
メリット4:専門家としての仕事が来る
専門家のライセンスは、クライアントからの依頼増加に繋がります。
これは「専門家としての専門知識を評価して…」とか、そういう話ではありません。
そもそも、大手クライアントの案件はディレクターが大体の導線を引いているので、書くべき内容はある程度決まっているのが普通です。
つまり、誰が書いても、ある程度同じ結論にたどり着くよう出来ています。
ユーザー層のリサーチから記事構成や目的までディレクションされた企画に対して、専門家ができることをいえば、
- 構成案の明らかな間違いを指摘したり
- ターゲット層に適した表現をしたり
- +αを提案する
程度です。
「では、クライアントは専門家に何を求めているのか?」
この答えはすなわち、「専門家」としての信用性にたどり着きます。
専門家としての信用性と表現力が、自社のコンテンツの質を高めてくれると信じているから依頼するということです。
メリット5:単価アップが期待できる
専門家は、依頼増加だけでなく単価アップも期待できます。
これについて、深く語る必要はないでしょう。専門家として一般的なライターが書けない「専門的なテーマ」のライティングを求めているケースです。
おそらく、この記事を読んだアナタもいちばんに「ありそうだな…」と思い浮かべたのではないでしょうか。当たり前のことを真っ先に書いても仕方ないので、あえて最後に書きました。
もっとも、普通のクライアントは専門家相手でも、いきなりこんなテーマを依頼しません。その専門家が「ペーパー」で、見当違いなコンテンツを作られてしまっては困るからです。
そのため、ふつうはメリット4のような「誰が書いても答えは同じ的なテーマ」で実力を調べ、改めて専門的なテーマを依頼。となるのが普通です。
「専門テーマだと、どれくらい単価が違うのか?」
これは、大手クラウドソーシングサイト「ランサーズ」の相場表を参考にすると良いでしょう。同サイトでは、
一般的なテーマ 0.5円~2.0円 / 文字
特定のテーマ 0.8 〜 3.0円 / 文字
専門的なテーマ 1.2円~5.0円 / 文字制作物の種類・参考価格(ランサーズ)
と、かなりの金額差をつけています。
まとめ
専門家としてのライセンスは、記事の信用力と発信力に大きな影響を与えます。
社会では【実務経験の方が大事だ】とする意見もありますが、ウェブライティングの世界では、ライセンスもまた大きな価値を持ってきます。(実務経験ナシでOKといっているわけではありません)
多くの人は、「専門家の言うことを正しい」と認識するからです。
もっとも、より大きな単価を求めるなら、【専門テーマに対応できる知識と経験】も必要です。こうしたテーマに対応するには、言うまでもなく実務経験が求められます。













